
この記事ではマルクスアウレリウスの『自省録』を紹介する。
この記事のポイント
- 自省録の内容がわかる
- 怒りや繊細さとの向き合い方
- 自省録の歴史
『自省録』は名言集ではない。ストア派に従い、感情に振り回されそうになる自分を、何度も理性で立て直そうとする記録。
一人の人間が「よく生きようと」と奮闘する姿が見られる。そんなローマ五賢帝のリアルな悩みを解説する。
もくじ
マルクスアウレリウス『自省録』の内容

ローマの五賢帝で、後期ストア派のマルクスアウレリウスが自分自身へ向けた日記のようなもの。怒りや絶望、自己嫌悪、時には自分を励ましたり、叱責が見られる。
そこには「立派な皇帝」というよりも、一人の弱さが赤裸々に書かれていて、その弱さをストア派の思想である理性によって整えようとしている。
怒りへの対処法
ストア派は情念(パトス)に流されず、常に理性的な状態を理想とした。とはいえ、マルクスも他者に対し「我慢ならない瞬間」はあったはず。そこで彼は怒りを押し殺すのではなく、理性により「無効化」しようとする。
次の一節は人間らしさがでていて、個人的にツボ。
腋臭(わきが)のある人間に君は腹を立てるのか。息のくさい人間に腹を立てるのか。(5・28)
以下では怒りに任せるのではなく、自分の判断そのものを考え直している。
他人の厚顔無恥に腹の立つとき、ただちに自ら問うてみよ、「世の中に恥知らずの人間が存在しないということがありうるだろうか」と。(9・42)
人が君にたいして過ちを犯したとき、その人が善悪に関するいかなる観念をいだいてこのような悪事をしたのか直ちに考えてみるがよい。それがわかったら、君はその人を憐みこそすれ、驚いたり怒ったりはせぬであろう。なぜならば君自身またその人と同じ善の観念を持っているか、あるいは大体同じような観念を持っているのだから彼を許してやらなくてはならない(7・26)
怒りを表へ出す前に、まず「そういう人間がいるのは当然」と前提を置く。怒りが残っていても判断を変えれば、炎は小さくなる。
マルクスは、怒りを憐みへと変え、許しを与える。理性によって情念の暴走を防いでいた。
戦場の自省録
自省録は戦場の陣営で書かれたけど、戦争の記録はほとんどない。
一例として
ひょっとしたら君は見たことがあるだろう、手、または足の切断されたのを、または首が切り取られて、残りの肢体から少し離れたところに横たわっているのを。(8・34)
人生は戦いであり、旅のやどりであり、死後の名声は忘却にすぎない。(2・17)
人に助けてもらうことを恥ずるな。なぜなら君は兵士が城砦を闘い取るときのように、課せられた仕事を果す義務があるのだ。もし君が足が不自由であって、胸壁を一人では昇ることができず、ほかの人の助けを借りればそれができるとしたらどうするか。(7・7)
こうした言葉から、戦場にいたマルクスの生々しい体験を覗き込める。自省録は戦略や、戦いの描写は少ない。
けれどマルクスの戦場の経験なしに、これらの言葉は生まれなかった。
閉ざされた自分のやりたいこと
マルクスの本心は哲学者として静かに学問の研究をしたかった。けれど運命は彼を皇帝に選んだ。
それでも彼は腐らず、「今すべきこと」に集中した。そんな彼の悲痛な心の内が見える。
生きることが可能なところにおいては善く生きることも可能である。しかるに宮廷でも生きることはできる。ゆえに宮廷でも善く生きることができるのである。(5・16)
これ以上さまよい歩くな。君はもう君の覚書や古代ローマ・ギリシア人の言行録や晩年のために取っておいた書物の抄録などを読む機会はないだろう。だから終局の目的に向かっていそげ。(3・14)
マルクスは学問の研究から身を引き、皇帝として生きる現実を受け入れている。
こうした自分のすべきことに集中する姿勢にストア派の思想が見える。
繊細な皇帝
ローマ皇帝で、教養もあったマルクスからは、繊細な一面が見られる。
人は田舎や海岸や山にひきこもる場所を求める。君もまたそうした所に熱烈にあこがれる習癖がある。しかし…君はいつでも好きなときに自分自身の内にひきこもることができるのである。(4・3)
この一節からは、静かな暮らしへの憧れや、皇帝としてのプレッシャー、激務から逃げたかったはず。
同時に、周囲からどう思われているのかを気にして心が揺れ、不安に駆られていたようだ。
間もなく君は死んでしまう。それなのに君はまだ単純でもなく、平静でもなく、 外的な事柄によって害を受けまいかという疑惑から解放されてもおらず、あらゆる人にたいして善意をいだいているわけでもなく、知恵はただ正しい行動をなすにありと考えることもしていないのだ。(4・37)
ここでは死を自分の近くに置くことで、名誉や評価など外的な事に支配されている自分を厳しく叱責する。
繊細で弱い自分を認め、理性によって心を立て直す。この取り組みは、アパテイア(不動心)へ近づくための内面的な鍛錬といえる。
マルクスアウレリウスが書いた『自省録』の編成
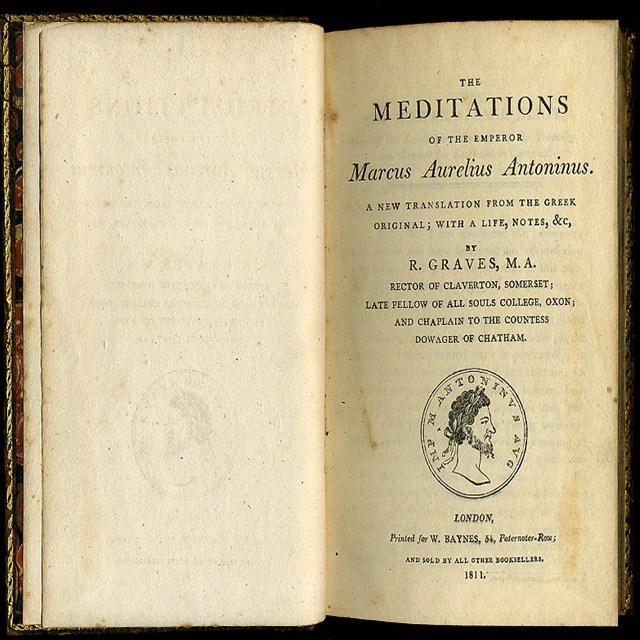
自省録は章ごとに整っていない。内容は断片的に書かれていたり重複する箇所もある。全文はギリシャ語で書かれていて、思考が書き並べられたノートに近い。
また自分への呼びかけである「君」が多く見られ、自分との対話が中心。
文体について
文体を観察すると4種類に分けることができる。
全体的に文章は短く素朴で、素っ気ない。これはマルクスの師であるルスティクスの影響がみられる。1巻の7にある「修辞学や、詩、美辞麗句をしりぞけること」とあり、飾り気のない文章を意識して書いたと思われる。
また「君」という呼びかけが多く見られ、心の声と理性の対話が書かれている。
自省録の成立
原題はギリシャ語で 「Τὰ εἰς ἑαυτόν(タ・エイス・ヘアウトン)」。訳すると自分自身へ。彼は晩年の10年間、遠征中の陣営で書きつづけた。
当時のローマでは母語がラテン語。けれど彼は幼いころからギリシャ語を学んでいて、哲学的な表現を用いるのに適していると考えギリシャ語で書いたのだと思う。
また『自省録』という題名は紀元10世紀ごろ後代の編集者によってつけられたとされる。
マルクスアウレリウス 自省録のまとめ
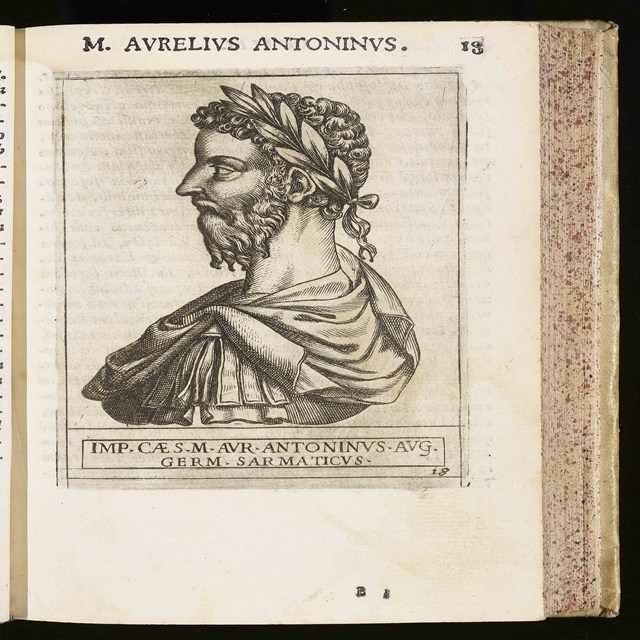
この記事ではマルクスアウレリウスの自省録を解説した。
今回のポイントは以下の通り。
自省録を読むとまるで自分に語りかけてくるような感覚を受ける。その内容は2000年以上たっても現代人の悩みを指摘し、時には叱責し、慰めてくれる。
人それぞれ自省録の言葉に刺さる内容は違う。実際に本書を手に取ってマルクスの言葉に耳を傾けてほしい。

